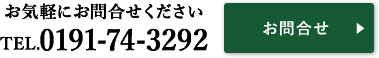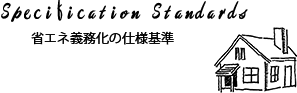2025年4月に予定されている建築基準法の改正は、新築住宅だけでなく、増改築や大規模リノベーションなどのリフォームにも大きな影響を及ぼします。
今回の改正では、「4号特例」(木造2階建て住宅などの一部設計図書の提出を省略できる措置)の一部廃止と、省エネルギー基準の適合義務化が主な変更点です。これは新築だけでなく、一定の規模や内容のリフォーム工事にも適用されます。
リフォームは既存の建物を基に行うため、以下のような点をより慎重に考える必要があります。
- 現行の建築基準法に適合しているか
- 増改築に伴う確認申請が必要か
- 新たな耐震基準や省エネルギー基準に準拠できるか
特に、以下のような建物では、法改正後の対応がより厳しくなると考えられます。
- 既存不適格建築物(建築当時は合法だったが、法改正により基準を満たさなくなったもの)
- 確認申請の履歴が不明確な建物(確認通知書はあるが、検査済証がないケースが多い)
- 都市計画区域外にある建物
これらの建物では、改正後に確認申請が必須となる可能性があり、構造計算書や詳細な図面の提出、追加工事による適法化が求められる場合があります。その結果、費用や工期に大きな影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、2025年4月の法改正を踏まえたリフォームの実務的なポイントや、より賢いリフォーム計画を立てるための視点について詳しく解説します
リフォームに関連するポイント
本改正の主な柱は下記の2点です。
-
省エネ基準適合の義務化
新築住宅だけでなく、一部増築・改修工事にも省エネルギー性能(断熱性能や省エネ設備性能)の適合が求められます。従来は新築に重点が置かれがちでしたが、今後は増改築部分についても省エネ基準適合が必要となる可能性があり、断熱材の改修や高効率設備の導入などが求められるケースが増えます。 -
4号特例の一部廃止による設計審査の厳格化
従来、木造2階建て住宅等(いわゆる4号建築物)に対しては構造図など一部図面の審査が省略されてきました。この特例が一部廃止されることで、増改築や大規模なリノベーション計画でも詳細な構造計算や設計図書の整備・提出が必要になります。結果的に、耐震性・防火性・避難計画などの確認が強化され、違反状態のまま改修を行うことが困難となります。
このように、リフォームにおいても建築基準法上の確認申請がこれまで以上に求められ、かつ省エネや構造安全性への適合性が徹底的にチェックされる流れが明確化されます。